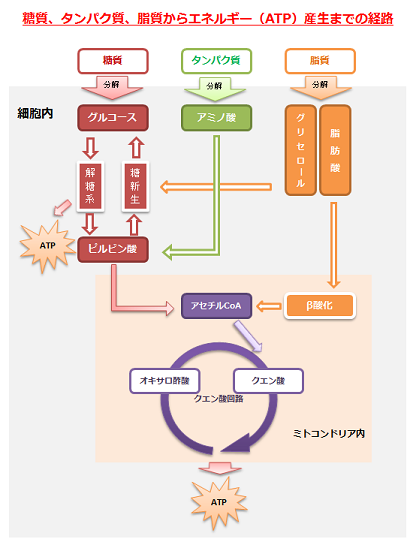何かと健康面で悪者扱いされる脂質。でも、脂質の中でも積極的に摂取することが推奨されている脂肪酸があります。その代表がαリノレン酸ですね。
私は、αリノレン酸よりも飽和脂肪酸の方が圧倒的に重要だと思っているのですが。
それは、とりあえず脇に置いておきましょう。αリノレン酸を多く含んでいる油として有名なのが、えごま油と亜麻仁油です。どちらかの油をスプーン1杯摂取すれば、1日に必要とされているαリノレン酸を補給できるということで、最近、注目されていますね。
でも、えごま油や亜麻仁油よりも、マヨネーズの方が手に入りやすく、手軽にαリノレン酸を補給できることは意外と知られていません。
1日に必要なαリノレン酸は約2グラム
厚生労働省の日本人の食事摂取基準2015年版によると、成人男性のオメガ3系脂肪酸の1日の食事摂取基準は2.0グラムから2.4グラムとされています。成人女性の場合は、1.6グラムから2.0グラムです。
αリノレン酸は、人間が必ず食事から摂取しなければならない必須脂肪酸でオメガ3系脂肪酸に分類されます。また、αリノレン酸は、体の中でドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を作る材料ともなります。これらの脂肪酸は青魚に多く含まれており、食べると頭が良くなるとか言われていますね。
αリノレン酸を摂取しようと亜麻仁油やえごま油をスーパーに買いに行っても見当たらないという方も多いのではないでしょうか?
私も近所のスーパーに探しに行ったのですが、見当たりませんでした。そこで、通販サイトで調べてみると、意外と値段が高く、こんなもの毎日飲んでられないですね。
マヨネーズのような脂質の多い調味料で十分
別にえごま油や亜麻仁油じゃなくても、αリノレン酸はマヨネーズに意外と多く含まれているので困ることはありません。
1回の使用量12グラム当たり約500mg含まれていますから、1日2回の使用で必要量の約半分を補給できます。残り半分は魚や肉を食べれば何とかなるのではないでしょうか?
また、αリノレン酸は、脂質の多い調味料に多く含まれている傾向にあります。フレンチドレッシング1回分にも360mg含まれていますから、マヨネーズと使い分けると良いでしょう。参考にマヨネーズ、フレンチドレッシング、牛脂、ラードに含まれる主な脂肪酸をまとめておきました。

なお、上記表はカロリーSlismを基にして作成しました。
カロリーオフとか脂質ゼロを謳っている調味料には、αリノレン酸は含まれていないので、利用価値なしですね。和風のドレッシングは、ほとんどが脂質ゼロなので栄養の補給になりません。
オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸の摂取量を同等にするのが理想と言われるが
オメガ3系脂肪酸とリノール酸に代表されるオメガ6系脂肪酸の摂取比率を1:1にするのが理想だと、健康番組でよく言われています。
私は、何となく怪しい気がします。
厚生労働省の日本人の食事摂取基準2015年版では、オメガ6系脂肪酸の摂取量は成人男性で8グラムから11グラム、成人女性が7グラムから8グラムとしています。なお妊娠中と授乳中の女性は9グラムです。
オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸の摂取量を1:1にするためには、オメガ3系脂肪酸を4倍から5倍多く摂取するか、オメガ6系脂肪酸の摂取量を2割程度まで減らすかのどちらかになります。
オメガ3系脂肪酸は健康に良いと言われており、オメガ6系脂肪酸は過剰摂取になっていてアレルギーの原因だという指摘があります。それなら、オメガ6系脂肪酸の摂取量を減らす方が良さそうですが、厚生労働省が約10グラムのオメガ6系脂肪酸の摂取基準を設けていますから、オメガ3系脂肪酸を増やすべきなのでしょう。
しかし、食事摂取基準2015年版には、「リスクに対する科学的 根拠が不十分なため、目標量(上の値)も算定しなかったが、α─リノレン酸多量摂取の長期間の影響はよく調べられていないので、過剰摂取には注意が必要である。」との記述があります。
これって、どこかで聞いたことがあるセリフではないでしょうか?
そうそう、糖質制限否定派の方々が、糖質制限は長期的予後がわからないので将来の安全性はわからないと言っているのと同じ理屈ですね。でも、糖質制限に否定的な医師の方でも、αリノレン酸の多量摂取が長期的にどのような影響を与えるかわからないとは言わず、αリノレン酸は健康に良いとばかり言っています。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」という言葉があるので、2グラムで十分なものをたくさん摂取する必要はなさそうです。オメガ3系脂肪酸もオメガ6系脂肪酸も不飽和脂肪酸なので酸化しやすく、血液をドロドロにすると言われていますからね。
とりあえず、毎日、マヨネーズを使っておけば、αリノレン酸の補給は問題ないでしょう。